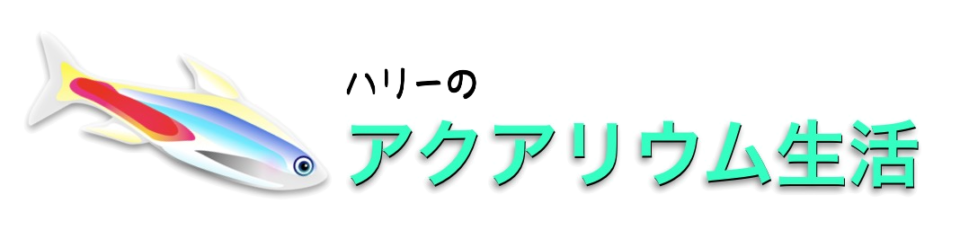熱帯魚の飼育において、適度なメンテナンスは必要となります。
今回はそのメンテナンスの一つである水換えについてご紹介しようと思いますが、この水換えの頻度や入れ替える水の量は飼育されている環境によって異なりますので、一概に「コレ」というのもがありません。
そこで、ここではタイプ別に分けて最適な水換えの頻度や量についてご紹介します。
スポンサーリンク
基本的な水換えの頻度や量について
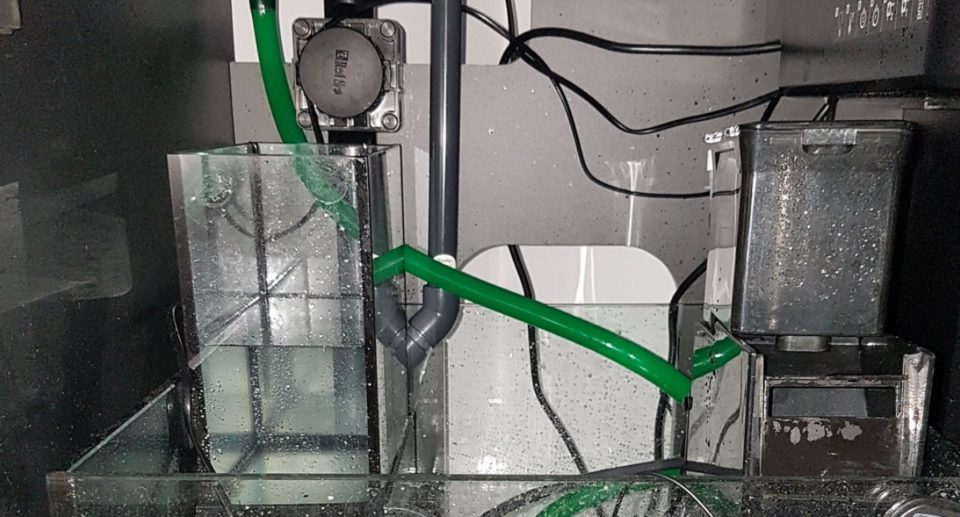
まずは、最適な水換えの頻度や量の平均的な水準についてご紹介しておきましょう。
ここで紹介するのはあくまでも平均値ですので、ここに記載する内容で水換えを行っても、急激に生体(熱帯魚など)に悪影響を与える様なことは起きないでしょう。
むしろ、最適な水換えの内容になっていることも多いので、水槽によってはベストな方法となるでしょう^^
平均的な水槽の水換えの頻度
まずは水槽内の水換えの平均的な頻度について。
平均値で言えば、1週間に1回の頻度が一般的に最適な頻度と言われており、最低でも2週間に1回のペースでは水換えを行う事が望ましいとされています。
もちろん、後述の水換えの量次第でこの「頻度」のさじ加減も変わってきますので、やはりあくまでも平均値ということを把握しておく必要があるでしょう。
平均的な水槽の水換えの量
続いては、水換えを行う際に1回の水換えでどれだけの水の量を交換すべきかという点について。
基本的には水槽内の1/3ほどの量を交換する事が望ましいとされています。
もちろん、この水換えの量に関してもあくまでも平均値であることを把握しておく必要がありますので、環境次第ではこれが最適ではないケースも発生するのです。

水槽別で最適な水換えの頻度と量について

それではここからが本題。
冒頭でもお話しした通り、水槽のタイプによって上記でご紹介の平均的な水換えの頻度と量が該当しないケースがあります。
なので、ここからはその水槽の状況別でオススメの頻度と量をご紹介しましょう!
エビ専用の水槽の場合
まずは、エビ専用で使用している水槽の水換えに関して。
人気で安価に手に入るミナミヌマエビを筆頭に、大きく金額が上がるレッドビーシュリンプなども水質の変化には非常に敏感に反応してしまう生体となっています。なので、急激な水質の変化はエビ達の体力を消耗してしまうことになりますので、水換えの量としては水槽の水量全体の1/4程度に留める様にしましょう。

ただ、水換えの頻度に関しては、元々エビが苔などを食べてくれる生体ですので、そこまで水質の悪化が早いわけではありません。よって2〜4週間に1回のペースの水換えでも全く問題ないと言えるでしょう。
過密飼育を行っている水槽の場合
続いてのパターンとしては、水槽の大きさに対して適正飼育数以上の生体を導入している水槽の場合についてです。
この場合は、水槽内での生物ろ過(バクテリアによる分解)が間に合わない速度で生体から排泄物が生産されますので、平均日数よりも早めの水換えが必要とされます。なので、過密度合いにもよりますが、3〜7日に1回の頻度での水替えが望ましくなってくるでしょう。
ただ、水換えの際の量に関しては、頻度さえ高めてしまえば一度に交換する水の量は水槽全体の1/3でも大丈夫ですので、ここはそのままの量で行う様にしましょう。逆に一気に大量の水換えを行ってしまうと、水中を漂っていたバクテリアが水槽外に排出されてしまい、水質悪化のスピードを早めてしまう原因にもなってしまいますので、ここは我慢しましょう。
過剰ろ過状態の水槽の場合
この過密飼育の水槽の水換えですが、例外が存在します。それは過剰濾過を行っている水槽の場合です。例えば、30cm水槽での飼育であるにも関わらず、60cm水槽対応の外部フィルターなどで濾過を行っている場合など、水槽の大きさに対して濾過フィルターの性能が高すぎる水槽で飼育されているケースです。
この場合は、想定されている濾過能力よりも高い浄化作用が働いている状態ですので、上記でご紹介の様な頻度で水換えを行わなくても、水質悪化を防ぐ事が可能となっています。
餌の食べ残しが多い場合
餌の形状や飼育している熱帯魚の食事の癖などの関係で、どうしても餌の食べ残しが水槽内に残る事があります。
もちろん少量の餌の食べ残しであれば、ミナミヌマエビやコリドラスなどを飼育している水槽であれば彼らが食べ残しを処理してくれるので、特に気にする必要はありません。
しかし、そういった掃除屋を飼育していない環境、もしくは掃除屋を飼っているが彼らでも食べきれない程の餌の食べ残しがある水槽の場合は水換えの頻度は高めに行う必要があります。
餌は当然ながら栄養価を豊富に含んでいるものですので、それを水槽内に放置することで腐らせてしまう事になりますし、餌の栄養分が水中に溶け出して水槽内の富栄養化を招いてしまう事もあるのです。
なので、普段から餌が大量に水槽内に残ってしまっている場合は、水換えの頻度をあげる様にしましょう。

水槽の変化が水換え頻度の目安に

この水換えの頻度に関しては、少しお値段は張りますが水質検査キットなどで水質チェックする事で、水換えが足りているのか足りていないのかを簡単にチェックする事ができます。
ですが、これとは別視点で水槽内のある変化を見る事で、水換えの頻度に関するヒントを得る事が可能なのです。
それはコケの量です!
水槽内が富栄養化の場合にコケが育ちやすい
というのも、前述でご紹介した餌の過剰添加による水槽内の富栄養化が進んでしまうと、その栄養素を養分としてコケが発生&爆殖してしまう事につながるのです。
もちろん、コケの発生には日照時間が長すぎるなどの要因も含まれていますが、日照時間を長くするだけではコケはじわじわ増える程度にしか影響はないので、急激に増えたりしている場合は飼育水の富栄養化が進んでいると疑って良いでしょう。
そして、この富栄養化の対処方法は非常にシンプルな方法で、単純に新しい水に取り換える、すなわち「水換え」を行えば解決する事ができるのです^^
水換えする事でコケの進行を抑制するだけで、コケ自体が物理的に無くなる訳ではありません。

生体の動きが鈍くなっている
水換えに関して、もう一つのチェック項目があります。
それは、水槽内に導入している生体の動きが鈍ってきている場合です。
生体の動きが鈍る原因としては、水質の悪化以外にも水温の低下・上昇だったり、寿命や(購入して間もない場合は)水槽に慣れてきただけなど、他にも要因が考えられます。
しかし、これらのどれにも該当しない状況で生体の動きが鈍ってしまっている場合は、水質悪化の可能性が高いので水換え頻度のUPを検討するべきでしょう。
注意
水換え当日〜翌日にかけて生体の動きが鈍ってしまっている場合は、逆に水換えによるストレスやダメージが出てしまっている状況と言えるでしょう。この場合は、次回以降は1回の水換えの「量」を少なく調整して水換えする様にしましょう。
水換えはアクアリウムに重要なメンテナンス

以上がアクアリウム水槽の水換えにおいて、最適な頻度と量となります。
アクアリウムのメンテナンスにおいて、そこそこ面倒な部類に入る内容ではありますが、生体の健康や景観維持にはかなり重要な項目ですので、気を抜かずにしっかりと対応できるようにしておきたいですね^^
スポンサーリンク